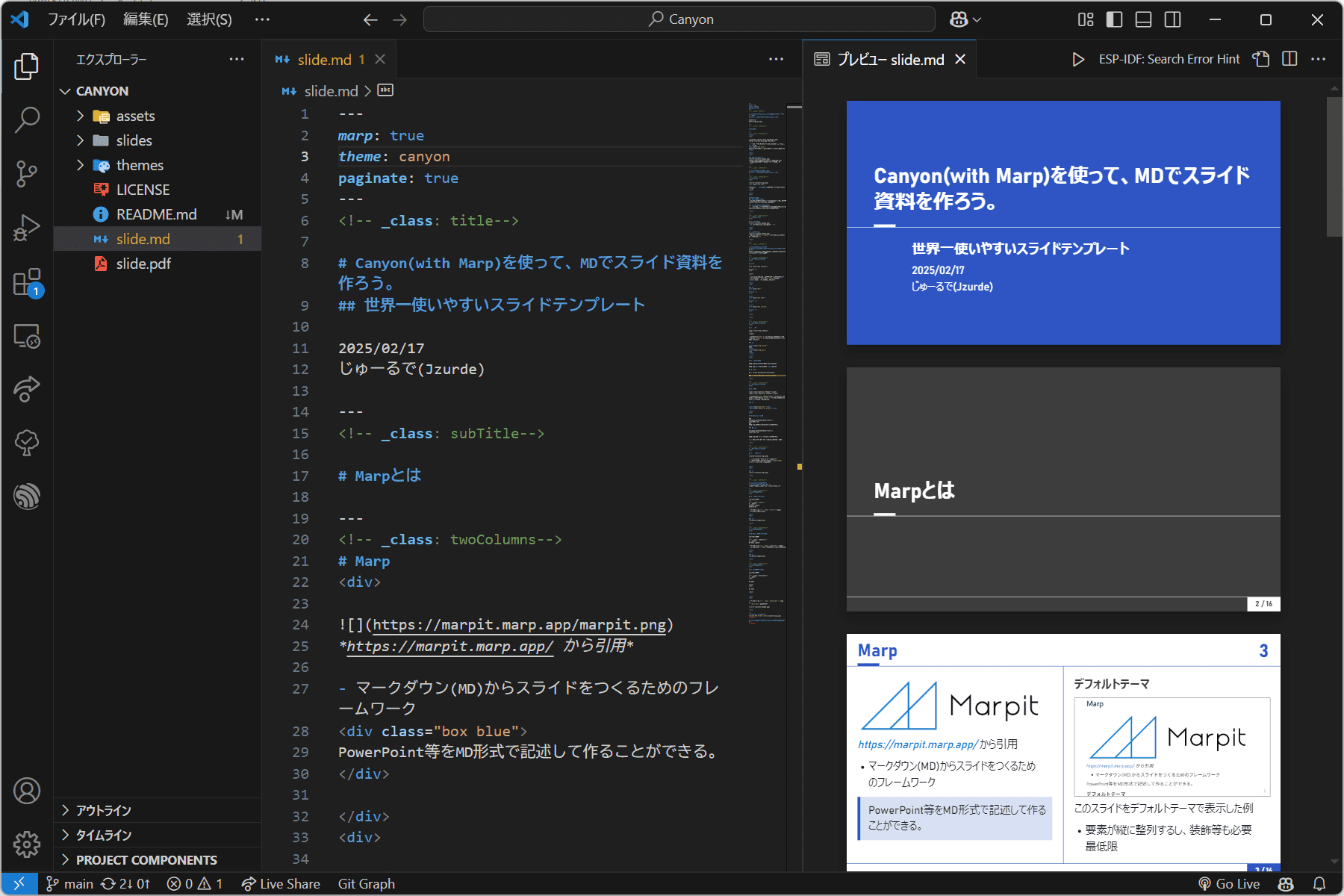異変
最初に異変に気づいたのはいつだっただろうか?
西武池袋本店を巡る大改装は突然始まった。私が異変に気づいたのは「西武スポーツ」が閉店したときだったかもしれない。その少し前の「ザ・ガーデン自由が丘」が閉店した時には、これから西武池袋本店で起こる大騒動にまだ気づけていなかっただろう。

2022年2月に百貨店西武・そごうの運営会社そごう・西武が、親会社のセブン&アイ・ホールディングスから売却される可能性が報道され、同11月に売却先はアメリカの投資ファンドに決定した。ストライキなどの騒動を経て2023年9月、そごう・西武は正式に売却され、アメリカの投資会社、フォートレス・インベストメント・グループ傘下に入った。
西武・そごう関連で大きな動きがあったようだとは認識しつつも、実際に何か変化が起こるのは少し先のことだろうと無意識に考えていた中で、実際に身近にあった店舗の一部が閉鎖していく衝撃は大きかったと言わざるを得ない。現在においては、2025年のグランドオープンに向けた改装工事中で、営業しているのは一部の売り場を除けば仮営業エリアのみである。
西武池袋本店で大改装という名の、大騒動が起こっていることは、すでに誰の目に見ても明らかなわけであるが、その経緯と意味を誤解している人は、意外にも少なくない。半分がヨドバシカメラになると聞いて驚く人もいるほどである。
本稿では、その意味で、これまでの復習である。何が起こり、どうなろうとしているのかという点をまとめ直すことを目的とした。
- [このページ] 改装の概要: 西武池袋本店はどのようになるのか
- [次のページ] 改装の経緯: なぜ西武池袋本店は減床することになったのか
改装の概要
百貨店西武・そごうの旗艦店であり、西武の本店でもある西武池袋本店は、2025年中のグランドオープンを目指し全館の改装工事を行なっている。
改装前と改装後のフロアプランを見て欲しい。ごく簡単にいうと、こう変化する。


売り場面積は88,000㎡から48000㎡とほぼ半減し、従来の中央ゾーン・北ゾーンはヨドバシカメラやそのテナントなどが入居する。ヨドバシカメラエリアについては、ヨドバシHDの石井スポーツや他の専門店が入居するほか、ヨドバシカメラの新業態(Yodobloom)が入居するという報道があったが、詳細は発表されていない。いずれにしても、大部分を家電量販店「ヨドバシカメラ」が占めるのは間違いないだろう。
立地
西武に残されたエリアは、一部を除いて、従来の南ゾーンと呼ばれるエリアである。この南ゾーンが西武池袋本店の立地においてどのような意味を持つのかは、周辺の地図を見ればわかりやすい。

西武池袋本店の建物は、JR線を中心とする池袋駅と中心が揃っていない。西武鉄道の看板を伴った東口の中央出口は、建物のおよそ北ゾーンと中央ゾーンの境目付近にあり、JRの看板のある東口北出口は、お隣PARCOの建物の1階部分に位置する。西武池袋本店の建物そのものが、池袋駅を中心に見れば南ゾーンなのである。
これは、地上以上に多くの人が行き交う、地下コンコースでも同じである。

地下コンコースの大動脈である、中央通路を東口方面に進むと、西武池袋本店の北ゾーンに当たる。その隣の南通路を通っても行き着くのは、中央ゾーンである。南ゾーンはそのさらに南側に位置する。西武池袋線の池袋駅からのアクセスは抜群であるが、それ以外のJR線や地下鉄線からのアクセスを考えれば、南ゾーンの立地が中央や北ゾーンに劣るのはいうまでもない。
予想されている改装プランをもとに、地下コンコースの地図を書き換えるとこうなる。

駅からのアクセスが良い部分にヨドバシカメラなどが入居し、西武に残されたのはかろうじて南通路の延長にかかる、建物の南側の部分だけである。ヨドバシカメラとライバル関係になるであろう東口の家電量販店、ヤマダ電機とビックカメラ本店は、いずれも地下から行こうとすれば地図右下の池袋ショッピングパークを通り抜けることになる。ヨドバシカメラはそれらと比較すれば駅直結という圧倒的に優れた立地を手に入れたわけである。
一方で、西武池袋本店が入る南ゾーンは欠点ばかりかと言われればそういうわけでもない。建物の形を見てみよう。
ウナギの寝床とも言われるこの建物は、実に横に長い。これは長所でもあり、欠点でもあるわけであるが、フロア全体を見通すことができず移動距離が長く感じがちな一方で、道のようなレイアウトを活用することで街の商店街のような楽しさを演出することもできる形状である。先が見通せないが故に、何が次に来るかわからない状態で道をぶらつくような楽しさを演出する試みも過去にあった。

見ればわかるように、南ゾーンは比較的正方形に近い形をしている。北ゾーンが、廊下みたいな形状をしていることと比較すれば、売り場としては使いやすい形状なのではないだろうか。また、エレベータ数も合わせて6機あり、うち4機は更新された新しい32人店員の大型エレベータである。エスカレータの配置を見ても悪くない。
また、別館・書籍館とパーキング(旧西武パーキング)とつながっているのも南ゾーンである。特にパーキングから繋がっている事実は大きく、例えば中央ゾーンや北ゾーンにあるヨドバシカメラに来た客も、自然と南ゾーンにある西武池袋本店を通ることになる。もちろん、駅からのアクセスの方が重要であることはいうまでもないが、富裕層を顧客に抱える百貨店であることを考えれば、駐車場からのアクセスも無視できるものではない。
さらに西武池袋本店が抱える顧客の内、西武池袋線沿線に住む割合を考えれば、西武池袋駅に近い南ゾーンは失いたくないエリアであるとも言える。
マーシャンダイジング
改装を端的に表す語句を考えると、プレスリリースなどで用いられた改装のテーマである「INCLUSION(インクルージョン)」と、「選択と集中」の2フレーズを挙げられる。比較的対極にある語句のように思えるが、実際に計画されている改装後の姿を表すという意味では適切な表現である。
INCLUSION
「INCLUSION」については、そごう・西武がプレスリリースの中で、「旧来の、婦人フロアと紳士フロアが分かれていた伝統的な“デパートメント(区分された)”ストアから脱却し、西武池袋本店は、池袋を訪れるさまざまなお客さまを、友人、カップル、家族が一緒にショッピングを楽しめる、自由で開かれた、かつ統一した空間でお迎えします」とその意味を説明している。
しかしながらINCLUSIONをイコール、婦人フロアと紳士フロアと分けるのをやめ1つのフロアにまとめるユニセックス展開、だと捉えるわけにはいかない。婦人服フロアと紳士服フロアはあくまでも1つの例として挙げているだけであり、そごう・西武が想像しているのは、より広い意味でもインクルージョン(包含性)であると推察できる。ヒントは2023年11月に新たに就任したセシア副社長の発言にある。
WWDJapanのインタビューの中で、「インクルージョンというコンセプトに対し、取引先の多くは賛同してくれた。(中略)トータルブランドなのに、シューズだけ靴売り場に置かれるとヘリテージとイメージがお客さまに伝わりにくくなる。」と述べている。要するに、ブランドの世界観とメッセージを伝えるためには、商品を商品のジャンルごとに分類することはできず、商品のストーリーに沿って並べる必要があるということである。その一例が商品のジャンルであるメンズ・レディースという括りで分類された婦人服フロア・紳士服フロアであり、当然、靴やカバン、雑貨といった区分も同じである。同じブランドのものは同じ場所に置きたいということである。
従来の売り場構成では、ある商品を配置するには、何らかの分類をする必要があった。例えばレディースであれば婦人服フロアに、女性用のカバンだったら婦人雑貨にといった具合である。しかし、価値観が多様になる現代社会においてこれは適切なのかという問いが生まれる。すなわち、ブランドのメッセージと世界観を持つ新たな商品が生まれた時に、百貨店が百貨店のデパートメント(区分された)構成であるが故に、ある商品をどこかに分類するのは、ある種の価値観の押し付けであるということである。そうであれば、区分をしない新たな売り場構成は、新たな価値観を受け入れるインクルーシブな売り場だと行っても飛躍はない。
選択と集中
改装後は「ラグジュアリー」「コスメ」「デパ地下」「アート」の4分野に注力する。いずれの分野においても、改装前よりも幅広いブランドや品揃えを確保する。
特にラグジュアリーをはじめとした高級品への集中は、百貨店における規定路線になってきている。自社開発商品を自社で販売する、ニトリやユニクロなどといったSPAと呼ばれる業態や、楽天、Amazonといったeコマースの発展により、小売業における百貨店の売上高の割合は減少傾向にある。これは、情報通信技術の発展に伴った動きであり、今後も情報通信技術を前提とした新たな業態の進化・発展の傾向は疑う余地もない。
しかしながら、高級品の販売においては、とりわけ「提案販売」において百貨店の役割は減少しない。高級品は額が大きいことや購入にある背景などにより、「失敗したくない」という心理が強く働く。その結果、販売員と対面で接してその場で説明を受けることができる百貨店で、ラグジュアリー商品をはじめとした高級商品に注力するのは理に叶う。
お店構成
ラグジュアリブティックの謎
マーシャンダイジングの一部である売り場構成も興味深い。そごう・西武の発表や各種報道の内容をもとに作った、改装後のフロアプランを再掲するので見て欲しい。

真っ先に目につくのは「ラグジュアリブティック」というものでなかろうか。「ラグジュアリ」は「贅沢な」「豪華な」「高級品」の意味で、「ブティック」はフランス語の小さな店や小売店から転じて「高級品やファッション製の強い洒落た衣服や小物を扱う専門店」の意味で用いられることが多い。婦人服・紳士服・高級雑貨などの旧来的な区分を取っ払って残った、「ラグジュアリブティック」という包括的なくくりは、はじめ違和感を覚えさせる。
違和感というのは、欲しいものが探しにくいのではないかという疑問である。狭くなったとはいえ、8フロアにもわたる売り場から思い描いている商品を見つけるのはこれまでも難しかったのに、括りが広くなったことで、さらに見つけにくい気がしてならない。この意図を汲み取るには、従来の日本の百貨店の根底にある前提と近年の社会の動きを参考にすることができる。
ワンストップショッピングと求められる変化
「ワンストップ・ショッピング」という言葉がある。従来の日本の百貨店は、「百貨」という言葉が示す通り、幅広い品揃えが特徴であり、強みであった。欲しいものは百貨店に行けば揃う。1つの建物に立ち寄ることで需要をまとめて満たすことができることを「ワンストップ・ショッピング」と呼んでいた。こうした店作りは、消費者がワンストップ・ショッピングをしたい、すなわち百貨店で全てを揃えたいと考えていることが前提となっている。
しかし、今日の消費者が依然としてそうした価値観を求めているかと言われれば、明らかにそうではない。何かが欲しいと思った時に、真っ先に百貨店が思い浮かぶ人は限られたごく一部の人間だけである。多くの人は、洋服はあそこ、食料はあそこ、スポーツ用品はあそこといったようにこだわりを持って店を選ぶようになった。その一部に百貨店を候補に挙げる場面もある程度である。
こうした中で起こるのが、前述の高級品シフトであるが、それだけではない。明確な目的を持った消費者は、SPAやeコマースなどで購入することもできる。百貨店という実店舗の強みを活かすのであれば、明確な目的を持っていない消費者に新たな選択肢を提案し、価値観を啓蒙することが重要になる。百貨店は元から提案型の販売を重視してきたものの、基本的な売り場構図についていえば、消費者が能動的に動き欲しいものを探し、百貨店はそれに応える形であった。これからは消費者が受動的になる番である。
「何がどこにあるのかわからない」がいい
商品を探すという意味では、細かな区分があった方が効率的である。しかしそれをやめ、何がどこにあるのかわからないという構図は、実は西武が以前にも取り組んだことがある「街づくり」である。
商店街や商業地区は、エリアごとに区分わけされてお店が並んでいるわけではない。通りを進んでいくと色々な予想もしていなかったものに出会うことが大半である。消費者は気付きさえもしなかった欲望を、偶然の出会いによって発見する。時に衝動買いとも言われるかもしれないが、こうした偶然の出会いは確かに生活に新鮮さを呼び込み、すっかり豊かになった消費者を虜にする刺激を持つ。
こうした街を模倣した売り場では、客は従来のように「仕事に来ていけるオフィスカジュアルのボトムスが欲しい」のような明確な需要ではなく、「おしゃれしたい」のような漠然とした需要を持ってやってくる。そこで出会うのは、レディースウェアかもしれないし、ユニセックスブランドの洋服かもしれないし、靴やカバンに目がいくかもしれない。旧来型の細かな区分を撤廃し「ラグジュアリブティック」という最低限の区分だけを残したことによってこそ、気づきの幅は広がるのである。
飛躍するようだが、これこそ究極のINCLUSIONなのだろう。これらは考察の域を過ぎないといえばその通りであるが、「店が狭くなったから苦し紛れに婦人服と紳士服をくっつけて誤魔化してる」といった浅はかな推測が散見される中で、今一度計画の奥深さの可能性を主張しておく。